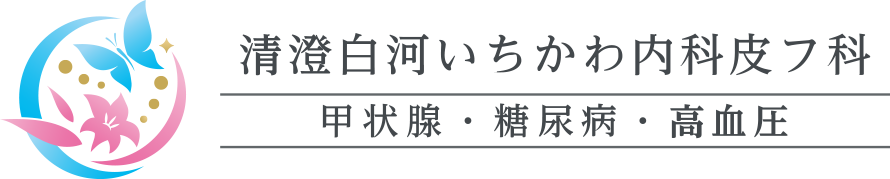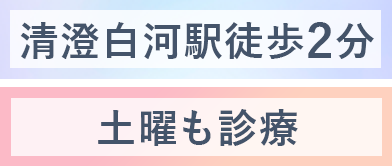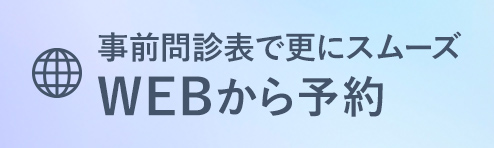このような症状はありませんか?
- 水っぽい鼻水
- 鼻がつまる
- くしゃみ
- 目がかゆいと感じる、ショボショボする
- 目が痛い
- 皮膚が乾燥する
- 喉が痛い、イガイガする
- 花粉症の薬を飲むと眠くなり、集中力が下がる
- 発熱・微熱が続く
など
 花粉症にはくしゃみや鼻水、目のかゆみだけでなく、発熱や皮膚の問題など、様々な症状が現れることがあります。これらの症状は生活の質を著しく低下させ、仕事や学業などにも支障をきたすことがあります。また、薬で症状そのものを軽減できても、眠気や集中力の低下に悩まされることもあります。
花粉症にはくしゃみや鼻水、目のかゆみだけでなく、発熱や皮膚の問題など、様々な症状が現れることがあります。これらの症状は生活の質を著しく低下させ、仕事や学業などにも支障をきたすことがあります。また、薬で症状そのものを軽減できても、眠気や集中力の低下に悩まされることもあります。
当院では、患者様のライフスタイルやご希望を考慮に入れた処方を行っており、できる限り日常生活を継続できるよう支援しています。花粉症でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
花粉症は内科で診療できます
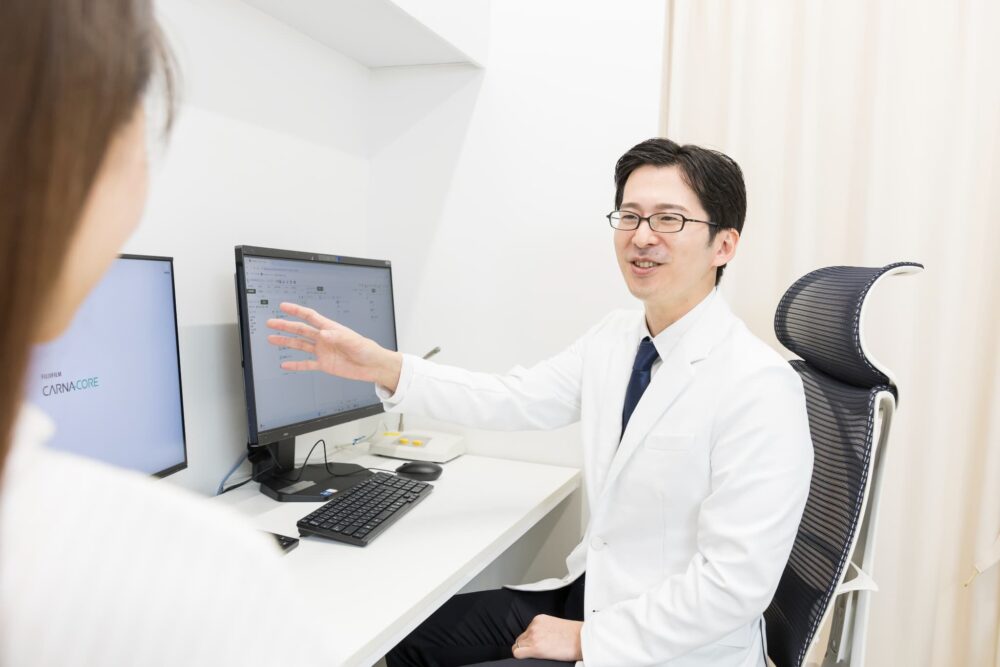 花粉症は季節性のアレルギー性疾患として発生します。症状としては、鼻水、鼻づまりやくしゃみだけでなく、目や皮膚のかゆみなどが挙げられます。
花粉症は季節性のアレルギー性疾患として発生します。症状としては、鼻水、鼻づまりやくしゃみだけでなく、目や皮膚のかゆみなどが挙げられます。
花粉症は一般的に、症状が早春から春にかけて現れるスギ花粉症が知られていますが、ヒノキやイネ科の植物など、他の植物の花粉によって発症するケースもあります。症状が強い場合や、市販の薬では眠気や集中力の低下に悩まされる場合には、医療機関を受診し、適切な治療を受けることをお勧めします。
当院は、花粉症の治療に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。睡眠時無呼吸症候群でCPAP治療されている方もCPAP継続のために花粉症治療が重要ですので当院で治療できます。
花粉症とは
アレルギー系の疾患の中でも、花粉症は「国民病」とされているほど多くの方が悩まされている疾患です。その患者数は増加傾向にあります。2019年の全国調査によると、日本人のおよそ3人に1人が花粉症だと計算されています。
花粉症の原因
スギやヒノキを原因とする花粉症の患者様が非常に多いことから、花粉症は春先に症状が現れる疾患として、一般的に考えられています。しかし、カモガヤやオオアワガエリなど、イネ科植物由来の花粉症は、初夏に症状が見られます。同様に、ブタクサやヨモギなどのキク科植物による花粉症は秋に症状が出ることがあります。さらに、複数種の花粉症を合併するケースもあります。
どの植物由来の花粉症であっても、抗アレルギー薬と花粉飛散時期における生活習慣の見直しによって、症状の改善が期待できます。
当院では、花粉とできるだけ接触しないための対処法なども指導しており、患者様の状態や生活様式に合わせた処方を行っております。お気軽にご相談ください。
花粉症の検査・診断
血液検査
患者様のアレルギー反応を引き起こすアレルゲンを特定するために、血液検査を実施しています。血清総IgE定量検査と血清特異的IgE抗体検査(RAST検査、MAST検査)を行い、花粉に対する特定のIgEの反応を確認することで、アレルゲンとなる植物を見つけ出します。
花粉症の治療
飛散時期の2週間ほど前から花粉症の治療を始めると、飛散期間中の症状が改善される可能性が高まります。スギ花粉症では「花粉飛散が始まると予想される時期の約1か月前」から抗ヒスタミン薬の服薬などを始めることを推奨しています。抗ヒスタミン薬を早めに飲み始めると、ヒスタミンの分泌もコントロールされ、症状が軽減されやすくなります。さらに、重い症状が鼻に出ている場合は点鼻薬を、目に出ている場合は点眼薬を処方することで、治療効果を最大限引き出します。症状が改善していなければロイコトリエン受容体拮抗薬などを追加します。
また、抗ヒスタミン薬の服用によって、眠気や集中力の低下に悩まされている場合には、これらの副作用が少ない薬の処方を提案しています。服薬についてお悩み・ご希望の治療方法などがありましたら、お気軽にご相談ください。
花粉症を予防するために
飛散時期が始まる前に、適切な治療を始めるだけでなく、花粉と接触する機会を最小限に抑える生活習慣を送ることも、症状の改善において欠かせません。以下の対策を参考にして、お悩みの症状を軽減しましょう。
- 外から帰ってきた後には、服についた花粉を玄関で払ってから家に入りましょう。
- 目や鼻、口など、症状が出やすい部位に花粉が入らないよう、外出時にはマスク、眼鏡、帽子を着用しましょう。
- 室内に入ったら、手洗い、洗顔、うがいを行いましょう。
- 外出時に着用した衣類は、寝室や居間など長時間過ごす部屋に持ち込まないように気を付けましょう。
- 布団や服などの洗濯物を外で干すのは避けましょう。
- 掃除時には、花粉を舞わせないよう拭き掃除をメインに行いましょう。
- 換気は短時間にして、空気清浄機を利用しましょう。
- 栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。
- 十分な休息と睡眠をとるように気を付けましょう。
- ストレスを解消する方法を見つけましょう。
花粉に触れる機会をできる限り回避し、部屋に花粉を持ち込まない生活習慣を意識しましょう。