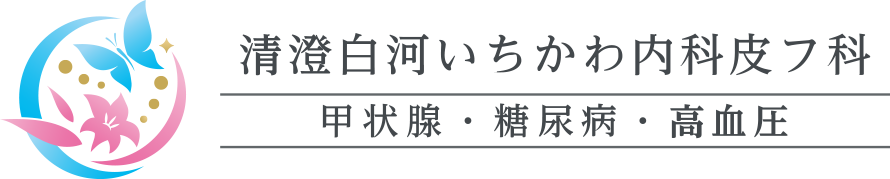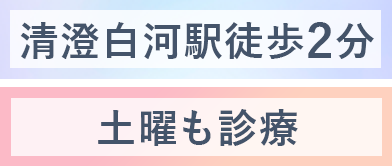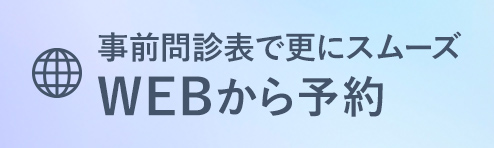甲状腺と不妊症、妊娠
 甲状腺ホルモンは体の成長や発達、代謝に必須のホルモンです。赤ちゃん自身の甲状腺が完成するのが妊娠約20週以降のため、妊娠前半ではお母さまの甲状腺ホルモンが赤ちゃんに移行することで、赤ちゃんの甲状腺ホルモンを維持しています。妊娠を希望する方や妊娠中の方では甲状腺ホルモンが適切な範囲で十分にコントロールできていることが非常に重要です。甲状腺機能亢進症 (バセドウ病など)や橋本病 (慢性甲状腺炎)などの甲状腺疾患は妊娠可能な年齢で多くみられることや、また、妊娠をご希望される方では通常と基準範囲が異なることから、妊娠前に一度甲状腺の検査をされることをお勧めします。
甲状腺ホルモンは体の成長や発達、代謝に必須のホルモンです。赤ちゃん自身の甲状腺が完成するのが妊娠約20週以降のため、妊娠前半ではお母さまの甲状腺ホルモンが赤ちゃんに移行することで、赤ちゃんの甲状腺ホルモンを維持しています。妊娠を希望する方や妊娠中の方では甲状腺ホルモンが適切な範囲で十分にコントロールできていることが非常に重要です。甲状腺機能亢進症 (バセドウ病など)や橋本病 (慢性甲状腺炎)などの甲状腺疾患は妊娠可能な年齢で多くみられることや、また、妊娠をご希望される方では通常と基準範囲が異なることから、妊娠前に一度甲状腺の検査をされることをお勧めします。
また、不妊治療の一貫で実施することがある卵管造影検査は、甲状腺機能に影響を与えることがありますので可能でしたら、実施前にご相談ください。
妊娠に影響を与える甲状腺疾患
甲状腺機能低下症 (橋本病など)と甲状腺機能亢進症 (バセドウ病など)があります。
甲状腺機能低下症では、次のような影響があります。
- 不妊 (排卵障害やホルモンバランスの乱れ)
- 流産・早産
- 妊娠高血圧症候群
甲状腺機能亢進症 (バセドウ病など)では次のような影響があります。
- 流産・早産
- 不妊
- 妊娠高血圧症候群
- 低出生体重児
- 新生児甲状腺機能異常
顕性の甲状腺機能亢進症では、不妊との関連や流産・早産の増加が報告されております。また、バセドウ病においては、お母さまの甲状腺自己抗体や内服中の抗甲状腺薬が赤ちゃんの甲状腺に影響を与えることがあります。そのため、妊娠前から適切に甲状腺機能をコントロールしておくことが大切です。
甲状腺自己抗体が赤ちゃんに影響を及ぼすことがありますので、甲状腺機能が正常、抗甲状腺薬内服していない状態や放射性ヨウ素内用療法後(アイソトープ治療後)、甲状腺手術後でも妊娠前に確認しておくことが重要です。
甲状腺疾患の症状
 バセドウ病では動悸、発汗過多、手の震えなどがありますが、潜在性甲状腺機能低下症 (FT4が基準値内でTSHが基準値を超えていること)ではほとんど症状がないことが多いです。そのため、症状がないからといって、妊娠前や妊娠中に治療が必要でないとは言えません。
バセドウ病では動悸、発汗過多、手の震えなどがありますが、潜在性甲状腺機能低下症 (FT4が基準値内でTSHが基準値を超えていること)ではほとんど症状がないことが多いです。そのため、症状がないからといって、妊娠前や妊娠中に治療が必要でないとは言えません。
甲状腺疾患の検査
 症状や身体所見に加えて血液検査と甲状腺超音波検査を行います。血液検査では甲状腺ホルモン (FT3, FT4)、甲状腺刺激ホルモン (TSH)、甲状腺自己抗体の評価をします。
症状や身体所見に加えて血液検査と甲状腺超音波検査を行います。血液検査では甲状腺ホルモン (FT3, FT4)、甲状腺刺激ホルモン (TSH)、甲状腺自己抗体の評価をします。
甲状腺疾患の治療
潜在性甲状腺機能低下症
潜在性甲状腺機能低下症 (FT4が基準値内でTSHが基準値を超えていること)は甲状腺ホルモンがわずかに少なくなっている状態です。流産・早産のリスクが高くなる可能性があります。そのため、TSHが高めの時には甲状腺ホルモン剤のレボチロキシン (製品名: チラーヂンS)を投与することが検討されます。
顕性の甲状腺機能低下症
顕性の甲状腺機能低下症 (明らかな甲状腺ホルモンの低下)では、不妊や流産率の上昇が報告されております。そのため、甲状腺ホルモン剤のレボチロキシン (製品名: チラーヂンS)を投与することが重要です。
甲状腺機能亢進症
バセドウ病の方は、妊娠ご希望時にメルカゾールを内服されている場合は他の薬に変更を行うことがあります。メルカゾールを妊娠初期に内服していると胎児奇形が増加する報告があるためです。メルカゾールをチウラジール、プロパジールに切り替えることが多いですが、副作用チェック期間中は副作用出現リスクが高いため、避妊をお願いしております。
また、内服薬量が多い時や、甲状腺機能が不安定な方はアイソトープ治療(放射性ヨウ素内用療法)や手術をご提案することもあります。
妊娠性一過性甲状腺機能亢進症
妊婦の2-3%にみられる妊娠初期の一過性の甲状腺ホルモン上昇のことを妊娠性一過性甲状腺機能亢進症と言います。胎盤から分泌されるhCG (ヒト絨毛性ゴナドトロピン)によって甲状腺が刺激されることで甲状腺ホルモンが上昇します。妊娠10週前後に多くみられますが、hCGはその後低下するため、妊娠14-18週頃には自然に改善します。通常は治療の必要はありませんが、ごくまれに症状が強い場合はヨウ化カリウム丸などを使用することがあります。バセドウ病と鑑別することが重要でTSH受容体抗体 (TRAb)陽性ならバセドウ病、TRAb陰性なら妊娠性一過性甲状腺機能亢進症の可能性が高いと判断します。
出産後の甲状腺検査・治療
検査
出産後に甲状腺機能異常を呈することがあります。破壊性甲状腺炎 (出産後甲状腺炎)は出産後2~4ヶ月に多く、バセドウ病は出産後4~10ヶ月に発症することが多いです。そのため、血液検査と、必要に応じて超音波検査も実施します。一般の方でも5-10%の頻度で出産後の甲状腺機能異常を呈するため、甲状腺機能検査をお勧めしますが、特に、甲状腺自己抗体陽性の方は出産後甲状腺機能異常を起こしやすいので、橋本病の方は出産後に甲状腺機能検査を受けることが推奨されます。また、バセドウ病の方は妊娠中に病勢が落ち着くことが多いですが、その反動で出産後に症状悪化する方が多いため、バセドウ病の方も出産後に甲状腺機能検査をお受けください。
治療
バセドウ病の方は甲状腺ホルモンの値や授乳の有無によって抗甲状腺薬を調整します。授乳中は、メルカゾールとチウラジールを安全に使用できる量の上限があるため、上限以上に増量が必要な際には赤ちゃんへの影響を懸念し断乳をお願いすることや、一定時間あけてから授乳をお願いする場合があります。また、ヨウ化カリウム丸については用量にかかわらず断乳を推奨しています。
妊娠前に顕性甲状腺機能低下症の方(明らかに甲状腺ホルモンが欠乏している方)は、出産後もレボチロキシン (製品名: チラーヂンS)を継続しますが、潜在性甲状腺機能低下症だった方は出産後から中止も検討します。