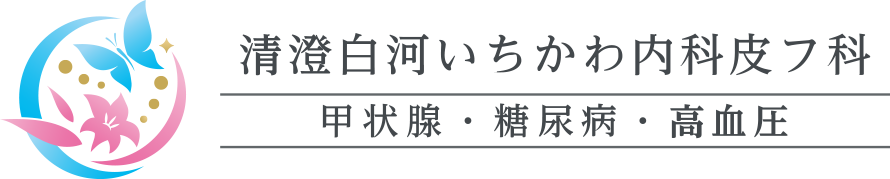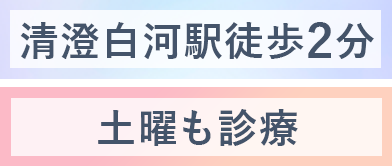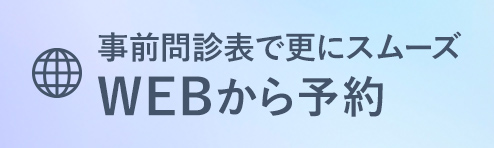甲状腺中毒症・甲状腺機能亢進症
(バセドウ病)とは

甲状腺中毒症は血液中の甲状腺ホルモンが過剰な状態のことをいいます。甲状腺中毒症の中で、甲状腺ホルモンを過剰に産生・分泌する疾患を甲状腺機能亢進症と言い、バセドウ病、機能性甲状腺結節、妊娠性一過性甲状腺機能亢進症などが該当します。最も頻度が高いのがバセドウ病です。甲状腺の機能が亢進した状態で、甲状腺ホルモンが多量に分泌されることで様々な症状が生じる自己免疫疾患です。一方、甲状腺ホルモンの合成は過剰となっていないものの、炎症などによって甲状腺細胞が破壊され、細胞内に蓄えられていた甲状腺ホルモンが漏出することで甲状腺ホルモンが高くなる病気を破壊性甲状腺炎と言います。破壊性甲状腺炎の代表的なものとしては無痛性甲状腺炎と亜急性甲状腺炎があります。無痛性甲状腺炎は慢性甲状腺炎 (橋本病)の経過中にみられることが多いですが、それ以外にも出産後や、アミオダロン、インターフェロンなどといった薬剤性によるものもあります。亜急性甲状腺炎はウイルス感染の関与が疑われていますが、未だに真の原因は不明です。(詳細はその他のよくある甲状腺疾患をご覧ください。)
原因
バセドウ病の原因としては抗TSH受容体抗体 (TRAb)という甲状腺に結合する抗体が持続的に甲状腺を刺激する結果、甲状腺が腫れ (首が腫れる)、甲状腺から多量の甲状腺ホルモンが分泌されます。「なぜバセドウ病を発症してしまったのでしょうか」というご質問をよくいただきますが、残念ながら、抗体ができる原因は未だに十分には解明されていないのが現状です。遺伝的要因や喫煙、出産などが関連する可能性は報告されてますが、正確な原因を特定することは難しいことが多いです。
症状

バセドウ病では甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで代謝が活発になり、様々な症状が現れます。代表的なものは次のようなものがあります。このような症状が続く際は早めに医療機関を御受診ください。また、男性では炭水化物の多い食事の後や運動後などに急に手足の力が抜けて動けなくなる発作が稀に起こります (周期性四肢麻痺)。
- 心臓がドキドキする (動悸)
- 汗をかきやすくなった
- 暑さを感じやすくなった
- 坂道や階段の上り下りで息切れしやすい
- 疲れやすい
- 目がでているように見える
- 食欲が増す
- 食欲があるのに体重が減っていく
- 下痢、便がやわらかい (軟便)
- 手が震える (手指振戦)
- 筋力が弱くなる
- 髪の毛が抜けやすい
- 足がむくむ
- 月経の異常 (月経不順、無月経)
- イライラしやすい
- 骨がもろい (骨粗鬆症)
検査
 症状や身体所見に加えて血液検査と甲状腺超音波検査を行います。血液検査では甲状腺ホルモン (FT3, FT4)の上昇、甲状腺刺激ホルモン (TSH)の低下、TRAbの上昇を認めます。血液検査と超音波検査でほとんどの甲状腺中毒症の原因は診断がつきます。
症状や身体所見に加えて血液検査と甲状腺超音波検査を行います。血液検査では甲状腺ホルモン (FT3, FT4)の上昇、甲状腺刺激ホルモン (TSH)の低下、TRAbの上昇を認めます。血液検査と超音波検査でほとんどの甲状腺中毒症の原因は診断がつきます。
脈が速い、不整脈などがある場合には心房細動などを起こすこともあるため心電図の検査を行うこともあります。
むくみが強い場合は、心不全を呈していることもあるため、胸のレントゲンを撮影することもあります。
ごくまれに血液検査と超音波検査で原因がはっきりしないこともあり、その際には院長が勤務している伊藤病院(表参道の甲状腺疾患専門病院)などでアイソトープ検査を実施することがあります。
治療
バセドウ病の治療は①薬物療法、②131I内用療法 (アイソトープ治療)、③手術の3つがあります。最初は薬物療法から開始するのが一般的です。
薬物療法では、チアマゾール (製品名: メルカゾール®)、プロピルチオウラシル (製品名: チウラジール®、プロパジール®)、ヨウ化カリウム (製品名: ヨウ化カリウム丸®)の3種類があります。妊娠初期以外の抗甲状腺薬の第一選択はメルカゾール®ですが、妊娠希望や授乳の有無などによってチウラジール®を選択することもあります。これらの薬は甲状腺ホルモンの合成を抑制する作用があります。
薬物療法開始後、採血で甲状腺ホルモンや副作用の有無を確認しながら抗甲状腺薬を減量していき、可能であれば中止を目指します。抗甲状腺薬中止後も再燃することがあるため、定期的に検査を実施する必要があります。
抗甲状腺薬で副作用を生じた際や、薬物療法を長期間実施していても中止できる見込みが少ない時、甲状腺悪性腫瘍を合併した時などは総合的に判断し、薬物療法以外の治療を選択していきます。甲状腺機能が不安定な状態で抗甲状腺薬の内服を長期間継続することはおすすめできませんので、適切なタイミングで薬物療法以外の治療を検討することが重要です。加齢に伴い、他のご病気の影響で、薬物療法以外の治療を実施しにくくなることもあるため早めにご相談ください。
当院では、甲状腺専門医の院長が適切に治療変更のタイミングをアドバイスいたします。アイソトープ治療や手術が必要な際は院長が勤務している伊藤病院(表参道の甲状腺疾患専門病院)などにご紹介させていただくことがあります。
抗甲状腺薬の副作用
抗甲状腺薬の副作用は、はじめの2~3ヶ月以内に生じやすいため、内服開始してから少なくとも2ヶ月間は、原則として2週に1回の定期的な診察と血液検査が必要です。
代表的な副作用としてはかゆみ、発疹、肝機能障害、無顆粒球症、関節痛、血管炎などがあります。
血糖値、脂質異常症、肝機能障害
との関連
甲状腺機能亢進症では、血糖値や脂質に影響を及ぼします。血糖値については、腸管での糖吸収が良くなるため、食べた物の吸収が増加し、食後の血糖値が高くなります。脂質に対しては、血清総コレステロールおよびLDLコレステロールが低値となり、中性脂肪(TG)も軽度低下することがあります。また、甲状腺機能亢進症では肝機能のAST、ALTが上昇することもあります。食後の血糖値スパイクや、健康診断でLDLコレステロールや中性脂肪の低下、肝機能障害を指摘された方は一度甲状腺機能検査をお受けいただくことをお勧めします。